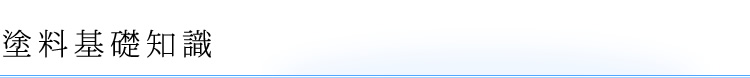1. 畜光塗料
畜光塗料は一般には夜光塗料と言われ、主成分は畜光顔料の働きにより太陽光や電灯などの外部光を蓄えて発光する塗料です。
畜光の機能自体は畜光顔料に依存しており、これに有機溶剤などのワニスを混合して塗料化されています。
製品的にはラジウムとZnS蛍光体を組み合わせたラジウム系畜光顔料を主成分とする塗料により開始され、その後、畜光顔料の低放射性の開発が進められてきています。
2. 蛍光塗料(蛍光体)
蛍光塗料は放電ガスにより紫外線で励起され可視光を生じる蛍光体を主要顔料とする塗料で、CRT・蛍光灯などのエレクトロニクス用途に利用される蛍光塗料です。
蛍光体は母体となる結晶中に少量の(Cu)など賦活剤が分散した状態の物質で、外部からの刺激(放電ガス)によりエネルギーを吸収し励起状態(高エネルギー)となり、励起状態から元の低エネルギー状態に戻る際に光を放出します。物質が吸収したエネルギーの一部または全部を光として放出するルミネセンス現象の一種で高熱を伴わないことから冷光とも呼ばれます。
代表用途としてはカラーテレビなどのCRT及びランプ(蛍光灯)に広く使用され、近年PDPにも基幹材料(蛍光ペースト)として採用されています。
3. 帯電防止塗料
帯電防止塗料は基本的にはEMI塗料と同じ導電性の塗料の一種ですが、EMI塗料は電磁波(電界)のシールドを目的としていますが、帯電防止塗料は静電気が帯電するのを防ぐのが目的です。
混入する導電フィラーは金属酸化物、カーボン、ニッケルなどがあります。
仕様目的は①情報通信分野の静電気障害の防止(塵やゴミなどの吸着現象といったクリーンルームの清浄度保持のトラブル防止、静電気放電の火花や熱による半導体部品などの破壊防止に目的が別れる)②石油プラントや危険物取り扱い工場などで静電気による引火や爆発防止などに使われます
4. 導電性塗料(電磁波シードル塗料)
このところ10年電子情報産業の発達は目を見張るものがあります。そこから発生する電磁波はほかの機械類そしてそれ以上に人体への影響も懸念されています。急速な対策を講じる必要性があります。
電磁波対策には導電性フィラーとバインダーから構成されフィラーとしてはニッケルや銀、銅やそれらの複合体から構成されます。現状としてはニッケルの採用が一般的です。バインダーとしてはアクリルやウレタンなどがあります。
5. マグネシウム合金用塗料
マグネシウム合金は、軽量化が図れる等の理由によりパソコン、自動車部品、家電製品、
OA機器、通信機器、放送機材等に使用される。特に近年ノートパソコンやデジタルカメラなどに使用される頻度が非常に高くなりその需要は大きなものになっている。マグネシウムという元素は無尽蔵にあるものなので資源として考えた場合非常に取り扱い安いものである。またマグネシウム合金の特徴として末端機器などの軽量化薄型化等のニーズにマッチするものである。
またリサイクル性にも優れていて環境面から見ても次世代の重要な素材として考えられる。
しかし、マグネシウム合金は腐食しやすいという欠点があるため、防食のための表面処理および塗料が不可欠となる
6. 耐熱塗料
耐熱塗料とは被塗物に塗装することにより高温にも耐えることの出来る塗膜を京成する塗料のことです。
主に自動車のエンジンかカバー、、オートバイのマフラー、ストーブやファンヒーターなどの暖房機器また化学プラント、石油プラントなどの大型プラントにいたるものまで幅広くしようされる機能性塗料です。
一般の耐熱塗料のほか耐沸騰水塗料や遠赤外線放射塗料などの特殊機能を有するのも耐熱塗料のひとつとして製品化されています。
また最近では1000℃を超える耐熱性能のある塗料の開発も進められています
7. 遮熱塗料
太陽光の主な熱エネルギー(熱線領域)である近赤外線を効果的に反射する塗料
外側表面に使用することで内部の温度上昇を抑制し、内部環境の改善・省エネルギー化を図ることが出来る
8. フッ素塗料
フッ素樹脂塗料は高い耐久性を発揮できる高耐候性塗料です。
高層ビルや公共性の高い大型建築物など、改修工事が困難な物件などはメンテナンスフリー期間の長いフッ素樹脂塗料などが広く使われています。
また塗膜表面を親水性にすることで雨筋などによる汚れを防止し、外観を保つ低汚染性塗料としての需要もあります。
タイプ別に分けると
溶剤可溶タイプの中低温焼付け、常温乾燥タイプ
溶剤分散タイプの高温焼付けタイプ
この塗料の主な使用先としては建築向けがメイン用途でフッ素樹脂塗料の約70%を構成しています。建築向けの中でも屋根や壁材、内装材など工場ライン塗装を行う製品での採用が中心となっています。
また橋梁や大型建築物など塗装が困難で、塗り替え回数を低減させたい物件での採用もあります。
10. 落書き防止塗料
貼り紙、落書きを寄せ付けない塗料
特徴;
塗膜は粘着テープや糊による貼り紙、マジックインキや塗料による落書きを寄せつけず、又簡単に除去できます
美しい景観、街並みは人々の心に安らぎを与えます。その中に氾濫する貼り紙チラシ・ステッカー、傍若無人な落書きを排除します
11. 制振・防音塗料
防音塗料と呼ばれるもののなかに制振塗料による防音効果をだすものがある。
不快、不要な音を低減するために音という現象とその原因である振動を低減させることを目的としている。
振動エネルギーを伝えないように反射または遮断してしまう。
主には建築・建材、産業機器・輸送用機器などに使用されている。
12. 発泡抑制塗料
発泡抑制粉体塗料
素材からの発泡(ワキ)を抑える塗料
特徴;亜鉛メッキ鋼鈑、アルミダイカスト、
鉄鋳物、マグネシウムダイカストなどに おいて、素材からの発泡を抑え、
ワキやピンホールのない良好な塗装が可能です
粉体の焼付時に素材の割れ部や素穴から発生するガスによる発泡を抑え素材の空焼きや、プライマーといった工程なしにワキやピンホールのない良好な塗膜が得られます
13. 親水性塗料
塗膜を親水性として、汚染物質の塗膜への浸透を抑制するとともに、表面に付着した汚染物質を雨水で洗い流すセルフクリーニング機能が働く。
外壁面の汚れ、特に雨筋汚れなどの抑止が期待できる
14. 帯電防止塗料(通電性塗料)
帯電防止塗料・・・塗膜に導通性を持たせ帯電を防止する(10・6~10・8MΩ)
導電塗料(導電粉体)・・・塗膜に導電性を持たせ静電気を防止する(10・3~10・6MΩ)
電磁波遮蔽・・・塗膜に導電性を持たせ電磁波を遮蔽(プラスチックを→金属)する機能
(10・-1~10・-3MΩ)
15. 粉体塗料
粉体塗料は、塗料中に有機溶剤や揮発性成分をいっさい含まない、塗膜形成分100%の微粉末で、粉末状のまま塗装して被塗物表面に塗膜を形成する塗料です。
特徴として①高品質(強度、耐薬品性、耐食性、耐候性などの性能バランスに優れる)②環境適合性(有機溶剤の使用無し)③安全性(塗装作業時における火災や中毒の危険性が少ない、臭気が無い)④省資源(溶剤処理装置などの設備不要、回収粉の再利用)⑤省力化・合理化(自動化が容易、ラインの小型化、塗装の専門家不要)などがあげられます。
塗装が簡単でしかも均一な仕上がりが得られるメリットがある反面、美装仕上げの際に、多めの塗装を施して塗膜独特のゆず肌面(平滑性に乏しい)を解消する必要がある。そのため厚膜となりコスト高につながる欠点が指摘されています。
国内で使用している粉体塗料の種類
①エポキシ
②エポキシ・ポリエステル
③ポリエステル
④アクリル
⑤変性
⑥EVA
16. 水溶性樹脂塗料
水溶性樹脂塗料は、塗料用合成樹脂の分子中に親水基を導入することにより水溶性とした塗料です。溶剤型における有機溶剤が見ずになった状態の塗料です。
水を溶剤としているため①火災の危険が少ない②爆発性の溶剤がほとんど存在しない③被塗物が多少濡れていても塗装可能、④大気汚染性や毒性が少なく環境対応度が高い等の特徴があります。
その反面廃水処理、蒸発速度が遅く温度や湿度の影響を受けやすい、凍結のおそれがある等の問題・課題点もあります。
高架方式により①焼き付け浸漬型②焼き付けスプレー型③常乾・強乾型に分けられます。
17. マイナスイオン発生塗料
塗膜からマイナスイオンが出る塗料
特徴:塗膜から安定したマイナスイオンを発生して精神のリラックス、血液の浄化、アレルギー症状の緩和、消臭・抗菌、抗カビ効果などがあると言われています
マイナスイオンの発生量は、半永久に持続します。
一般の焼付け塗料(粉体・溶剤)と塗膜性能は変わりありません。
用途:
スチール家具、家電製品、学校や病院等の屋内設備
18.プラスチック用塗料
塗膜をつけることの目的として成形品の外観デザイン性を付与することや表面硬度(耐スクラッチ性)、耐紫外線、帯電防止性などの表面機能を付与することなどがある。
合成樹脂塗料としては、溶剤型・水溶型・無溶剤型などがある。
プラスチック其材の塗料としては溶剤型が多く使用されている。
硬化乾燥方法としては、常温乾燥・加熱乾燥(赤外線乾燥、熱風乾燥)などがあるがプラスチックの性質上乾燥温度などの影響を考慮しなくてはならない。